基本情報
バケツ稲(ミニ田んぼ稲)に挑戦!自分たちだけの小さな田んぼで稲を育てよう!
2020.10.2

苗植えから収穫まで、バケツやミニ田んぼでの稲作を通じてお米に関する学びを深めましょう。
2~3株の苗を植えたバケツ1つで、うまく実ればお茶わん約1杯分、3,000~4,000粒ものお米を収穫することができます。
自分たちだけの小さな田んぼで、毎日少しずつ変化する稲の生長を観察してみましょう。

お米の出前授業
東京都の小学5年生向けに、バケツやミニ田んぼでの「苗植え実習」や、そこで実った稲からお米(玄米)にする「脱穀・籾摺り実習」など、体験を通じてお米についての理解を深める出前授業を行っています。
はじめに
1. 用意するもの
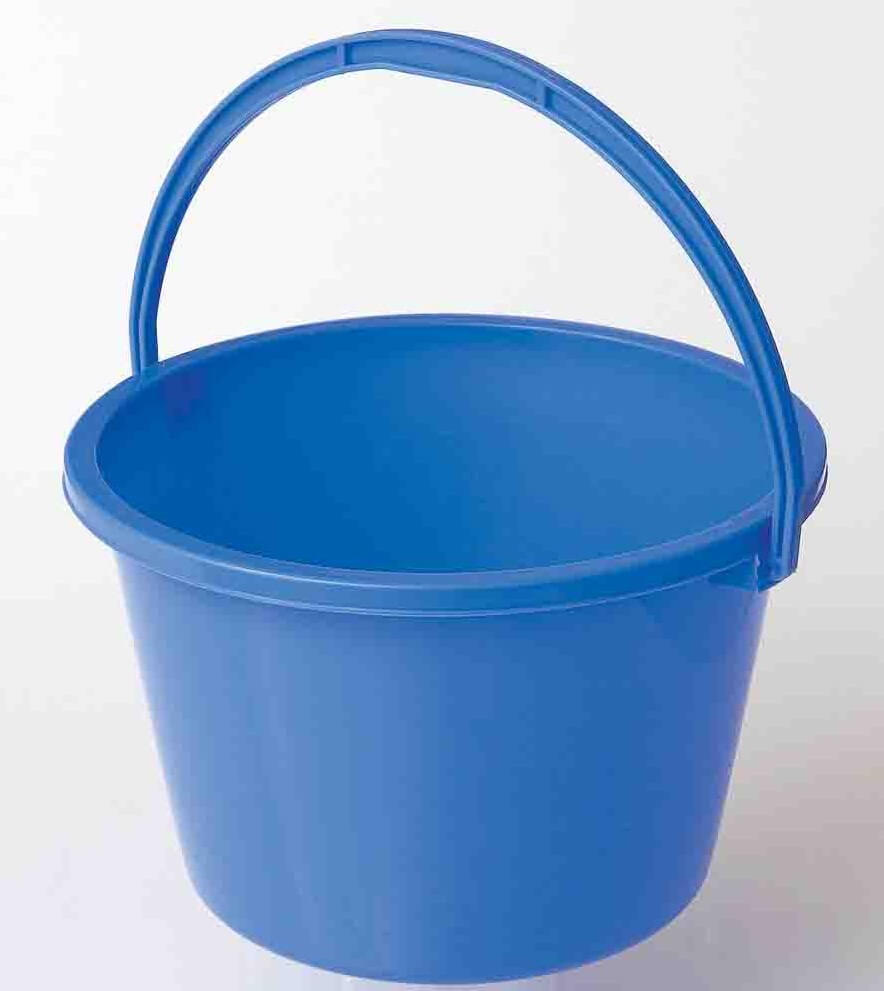
バケツ
9.5ℓ(リットル)前後の大きさのバケツを用意しましょう。稲がのびのびと育つように、直径が30㎝以上あるものがおすすめです。
苗植えをした後に、学校の所定の場所までバケツを運ぶ必要がある場合、あまりにも大きなバケツですと、土に加え水も入りますので、相当な重量となり、小学5年生の力では持てなくなってしまいますのでご注意ください。

水
水道の近くが良いですが、もし近くに水道がない場合には、ホースなどを用意しておきましょう。

苗
パルシステムでの「お米の出前授業」では、パルシステムの提携産地にて育苗(いくびょう)した苗を用意しています。

土
「黒土」「赤玉土」「鹿沼土」を6:3:1の割合で混ぜたものがおすすめですが、花壇の土や、以前にバケツで稲を育てた時の土が残っていればその土をそのまま使っても大丈夫です。その場合には、水を早めにはって、土をやわらかくしておきましょう。もし土が固い場合には、一度外に出してくだいてください。土の中に根やくきが残っていても大丈夫です。
土がない場合には園芸店やホームセンターで購入(こうにゅう)できます。肥料(ひりょう)入りの土を使っても問題ありません。
2. 前準備

バケツに土を入れましょう
土は7ℓ(リットル)程度入れます。バケツ一杯に入れてしまうと、水を入れたときにあふれてしまいますので、気を付けてください。

ミニ田んぼの場合には事前に水をはっておきましょう
前に使った土が入っていれば、そのままその土を利用すれば大丈夫です。土が少ないようでしたら花壇の土や園芸店、ホームセンターで購入(こうにゅう)し、土を足しておきましょう。
ミニ田んぼに水をはるのはけっこう時間がかかるため、前もって水をはっておきましょう。水を早めにはって、土をやわらかくしておくとよいです。

水をはる前に土を平らにしておきましょう
表面が平らになっていないと水に浸る部分とそうでない部分とができてしまいます。
平らにならした土の表面に少したまるくらいまで水を入れましょう。2~3㎝程度の深さでよいです。
もし土が固い場合には、一度外に出してくだいてください。土の中に根やくきが残っていても大丈夫です。
素足で田んぼに入るのが嫌な場合には、画像のように長靴をはいたり、すのこに乗って田植えしたりするのも良いです。必要に応じて用意しましょう。
田植えの手順

1. 水を入れましょう

バケツに入れてある土の表面を平らにならしましょう。表面が平らになっていないと水に浸る部分とそうでない部分とができてしまいます。
平らにならした土の表面に少したまるくらいまで水を入れましょう。
2. しろかきをしましょう

土の表面から5㎝くらいの深さまで手でかき混ぜます。表面から2㎝くらいは、さらにどろどろになるまでかき混ぜます。
しろかきをしたら、土と水をまじませるために10分くらいそのままおきましょう。
3. 苗(なえ)を植えましょう

苗(なえ)は根っこを切らないように横に引いて分けます。

苗(なえ)はバケツのふちから5㎝ほどはなして、苗(なえ)と苗(なえ)の間を7~8㎝ほどあけて植えましょう。
バケツの直径の大きさにもよりますが、2か所、または3か所に植えるのが良いです。

植える時の深さは人差し指の第2関節(約5㎝)くらいが目安です。
4. ミニ田んぼの場合には等間隔にてまっすぐに植えていきましょう

ミニ田んぼの場合も、植える時の深さは人差し指の第2関節(約5㎝)くらいが目安です。

まっすぐ列になって植えることができています。

苗と苗との間を均等(きんとう)に保って植えていきましょう。苗と苗との間隔は手の指先から手首までの長さよりちょっと長いくらい、20㎝~25センチくらいあけましょう。まっすぐに植えていけるように、ひもなどをはって目印とするのも良い方法の一つです。
5. 余った苗はとっておきましょう

苗が余ったら、予備として水をひたしたトレーなどに入れて、ミニ田んぼであればその隅のほうにそのまま置いておくなどして、とっておきましょう。うまく生長しなかった苗があれば、それのかわりに植え替えてあげましょう。
観察

1. 分けつして増えた苗を観察しましょう

生長がすすむと茎(くき)の数が増えはじめます。1本の茎(くき)がなんと10倍にも増えます。これが過ぎれば、穂(ほ)が出るのももうすぐです。
2. 雑草かな…?

苗植えをして数日がたつと、雑草らしきものがいろいろと…。化学合成農薬を使わないからこそ、みなさんの小さな「田んぼ」では苗の生長にともなっていろいろな姿を観察できます。
どうしたらよいか…。そんな時は生産者のアドバイスに耳をかたむけてみましょう。
「お米博士を目指そう!おにぎり先生と学ぶお米ものしりコーナー!」の、「雑草…?でしょうか?」に生産者が詳しく解説してくださっていますので、見てみてください。
3. 花を観察しましょう

稲(いね)の花。身がふたつに割(わ)れ、中から白いおしべが飛び出します。午前10時前後から2~3時間ほどしか開花しません。
4. ネットをかけましょう

稲の穂が出てきたら、すずめなどに稲の穂を食べられてしまわないように、ネットをかけると良いです。

お米博士を目指そう!おにぎり先生と学ぶ お米ものしりコーナー!
こちらのコーナーはみなさんからいただいたお米についての「なんで?」「どうして?」といった問いについて、パルシステムのお米の生産者や職員がお答えします!
身近な食べものであるお米についておにぎり先生と一緒に学んでお米博士になろう!
稲刈り・乾燥

1. 稲刈りをしましょう

稲刈りは、穂が出てから40~45日くらいが目安です。穂が全体的に黄色くなり、10粒のうち9粒くらいが黄色くなったら刈り取りましょう。
稲刈りの方法は、稲の根元から5㎝くらいのところを、はさみなどで切ります。はさみは園芸用のものでも、普通の文房具用のものでも、どちらでもかまいません。
2. 稲を干して乾燥(かんそう)させましょう

刈り取った稲の根本をひもなどで束ね、日当たりの良い場所で10日ほど干します。屋外(おくがい)で乾燥させる場合には、鳥などに食べられてしまわないよう、ネットをはるなど気を付けましょう。乾燥した稲が落ちるので、下には新聞紙などを敷いておくのも良いです。

茎(くき)がカラカラになったらいよいよ稲からお米をとります。
脱穀(だっこく)・籾摺り(もみすり)

1. ボールとすり鉢を用意しましょう

パルシステムでの「お米の出前授業」では、小学5年生がにぎりやすい大きさの軟式野球ボールとすり鉢を用意しています。軟式野球ボールは適度な硬さのゴム製素材のため、すり鉢が割れてしまうようなことがないため適しています。
2. 穂から籾(もみ)をはずしましょう

穂から籾(もみ)をはずすことを脱穀(だっこく)といいます。手で籾をしごくと簡単です。籾(もみ)や籾殻(もみがら)が飛び散るので、新聞紙を敷いたり、大きなポリエチレン袋の中に手を入れて作業すると後で掃除が楽です。
3. ボールとすり鉢を使って籾摺り(もみすり)をしましょう

脱穀(だっこく)した籾(もみ)の籾殻(もみがら)を取り除くことを「籾摺り(もみすり)」といいます。脱穀した籾(もみ)をすちばちに入れて、野球ボールなどでゆっくりとこすりましょう。

乾燥したお米は割れやすいので、力を入れすぎないように気を付けてください。
4. 籾殻(もみがら)を取り除きましょう

籾殻(もみがら)が取り除けたら、やさしく息を吹きかけたり、うちわや下敷きなどであおぐなどして、籾殻(もみがら)を吹き飛ばしましょう。軽い籾殻(もみがら)は風に乗ってボールの中から外に向かって飛ばされます。こうしてボールの中に残ったものが玄米(げんまい)です。
5. 玄米になりました

収穫(しゅうかく)のあと、乾燥(かんそう)や脱穀(だっこく)、籾摺り(もみすり)をして、「玄米」、やっと食べられるお米になりました。玄米のまま食べても良いですし、「精米(せいまい)」をして表面のぬかをとりのぞき、「白米(はくまい)」として食べても良いです。














